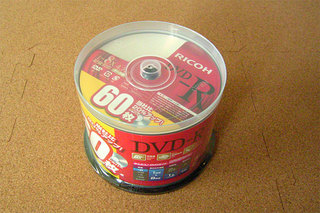SVX日記
2006-08-11(Fri) アキバる
休み終盤。グダグダと漫画のデスノートを読みふけっては、ニンテンドーDSのテトリスの通信対戦を繰り返し、順調に一週間の休みを無駄に過ごしつつある今日この頃だが、一度も行かないワケにもいかんだろう(?)……と、いうことで、秋葉に行く。
例によって、アチコチとゲーセンを回るが、なんだかアレだねぇ、興味のあった「連合vsZAFTII」も前作と代わり映えしないし……デストロイに乗ってみたかったんだが、プレイヤとしては乗れないし。対COM戦をしようにも、対戦台ばっかりだし。入っても瞬殺されるのわかってるからヤル気せんわ。グラディウスして、グラディウスIIして、19XXして、レイクライシスして……はなまるうどんでしょうゆうどんの大盛りを食って……なんだか、コッチも代わり映えしない。
2014-08-11(Mon) 早朝撃破
2016-08-11(Thu) ラズベリーパイ(Raspbian)で無線LANブリッジする
CUIで無線LAN接続に成功したものの、アホな無線ルータに散々に悩ませられたが、ローエンドな無線LANルータを買って解決。次なる目標はラズベリーパイをルータにすることだ。こんな感じに。
……んが、ラズベリーパイをルータにすると、対象機器へのルーティングの定義が必須となる。めんどい。ここは、ラズベリーパイもブリッジとするべきではないか。それならば、対象機器へのIPの払い出しも、宅内LANにつながっているLinuxルータで一括管理できるし。
root@xxxpi:/etc/network# diff -bc interfaces.org interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
! iface eth0 inet manual
! allow-hotplug wlan0
! iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
--- 9,27 ----
auto lo
iface lo inet loopback
! auto eth0
! iface eth0 inet static
! address 0.0.0.0
! auto wlan0
! iface wlan0 inet static
! address 0.0.0.0
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
+ auto br0
+ iface br0 inet dhcp
+ bridge_ports eth0 wlan0……と、できてみれば単純な設定だが、無線の設定とも絡んで、かなり手こずらされた。無線の設定は、先日の/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confに設定しておけばいい。
root@xxxpi:/etc/network# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr aa:bb:cc:dd:ee:52
inet addr:172.xx.xx.xxx Bcast:172.xx.xx.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr aa:bb:cc:dd:ee:52
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr aa:bb:cc:dd:ee:74
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1ブリッジが形成されると、ブリッジのメンバであるeth0とwlan0にはIPアドレスが割り当てられなくなり、br0にIPアドレスが割り当てられる。ブリッジはレイヤ2動作のため、当然、IPアドレスを持たないのだが、このbr0のIPアドレスはブリッジの上にいる自ホストに割り当てられたIPアドレスという感じか。はじめて目にした時にはかなり混乱し、理解するまでに時間を要したっけ。
root@xxxpi:/etc/network# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.xxxxxxxxxxxx no eth0
wlan0先日から愛用しているミニコンポを有線LAN接続するのである。
これにより、ミニコンポからは有線LAN接続でDLNAサーバにアクセスし、音楽を再生できるようにはなったのだが、なぜかラズベリーパイ上で宅内LAN上のサーバへのnfsアクセスが不安定。fstabに書いておいても起動時にmountしてくれないし、以下のコマンドでmountできる時とできない時がある。またしても無線LANブリッジが怪しいのだが、不安定なだけに調べようがない。うーむ、どうしてくれよう。
root@xxxpi:~# systemctl start rpcbind
root@xxxpi:~# mount /mnt/mediatomb/2023-08-11(Fri) コンテナ上にリモートデスクトップ環境の構築に成功
だいぶ間が開いてしまったが、東北から戻ってから、自宅の外壁工事が始まったり、ロードスターを外の駐車場に退避しておいたらブツけられたり、筋トレを緩めたせいなのか体が緩んだり、なんやかんやで、どうも気分的に不安定になっていたりする。
男性にも更年期があるとかで、そのせいなのか、自宅やクルマというテリトリが侵され気味のせいなのか、仕事の環境が微妙なせいなのか、暑い中を動きすぎて塩分が足りてないのか、どうも気分は曇り空である。時々、晴れ間が覗くような、そうでもないような。
何かに取り組んでいないと気がすまない性格なのに、どうも取り組む気が起きず、ダラダラとゲームしたりしてしまう。ゲームが悪いわけではないのだが、そういう気分の時にゲームすると罪悪感のようなものを感じてしまって、ますます気が滅入る。我ながら面倒くさい性格とは思うのだが。
そんな日々の中、今日はすっかり存在を忘れていた休日なのだが、なんとなく気分に晴れ間が覗いたからか、以前から作ってみたいと思いつつ、ディスクの容量などの都合で断念していた「リモートデスクトップコンテナ」の構築を始めてみた。
自分はFedoraでMATEの人なのだが、コンテナのビルドで「MATEデスクトップ」をインストールしようとすると、なぜかディスクの容量制限にかかって失敗してしまうのだ。そんなら、ということで、姑息ながら小分けインストールしたみたところ、そんな方法でインストールに成功してしまった。
突き詰めていくと「MATE」と「MATE Desktop」に分けるだけで十分なようだ。何度かつながらない状況をトラブルシュートしながらアレコレした程度で、それほど苦労することもなく、アッサリと「リモートデスクトップ接続(RDP)」からの接続に成功してしまった。
# cat Dockerfile
FROM fedora:38
LABEL maintainer="Furutanian <furutanian@gmail.com>"
ARG http_proxy
ARG https_proxy
RUN set -x \
&& dnf groupinstall -y 'MATE' \
&& dnf groupinstall -y 'MATE Desktop' \
&& dnf install -y xrdp \
&& rpm -e thunderbird thunderbird-librnp-rnp \
&& rm -rf /var/cache/dnf/* \
&& dnf clean all
RUN set -x \
&& ln -sv /usr/lib/systemd/system/multi-user.target /etc/systemd/system/default.target \
&& systemctl enable xrdp \
&& systemctl disable firewalld
EXPOSE 3389
ENTRYPOINT ["/sbin/init"] # cat docker-compose.yml
version: '3'
services:
crd:
image:
docker.io/furutanian/crd
container_name:
crd-alpha
build:
context:
.
# args:
# http_proxy: http://user_abc:password@proxy.example.com:8080/
# https_proxy: http://user_abc:password@proxy.example.com:8080/
ports:
- "13389:3389"
restart:
always
stop_grace_period:
1s
privileged:
true
environment:
TZ: Asia/Tokyo
# http_proxy: http://user_abc:password@proxy.example.com:8080/
# https_proxy: http://user_abc:password@proxy.example.com:8080/
volumes:
- pv:/home
volumes:
pv:
driver: local
# データを永続的に保持する領域として
# mkdir -pv pv しておくこと
driver_opts:
type: none
o: bind
device: $PWD/pv一応、/homeはPVに出してあるが、コンテナなので再起動すると、良くも悪くもほとんどの設定がブッ飛んでしまうし、現状、コンテナを上げる都度、ユーザを作らなければならないし、英語環境だし、キーボードはヘンだし、タイムゾーンはUTCだしで、まだ詰めは甘い。が、そのへんの直しとか、愛用のメーラであるMAVEの導入とかは、このコンテナを継承する形にするべきで、これはこれで完成形かな。
しかし、これが完全に実用になったならば、常に最新のFedoraに乗り換え続けることも容易になるな。これは、Windowsを捨てFedoraに移行して以来のデスクトップ環境の革命かもしれん。