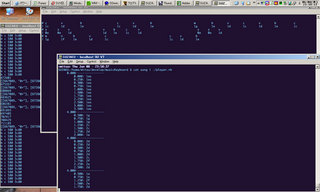SVX日記
2004-06-08(Tue) 工作2題
というわけで、今日は昨日の「車版フライトレコーダ」の構想について書いてゴマかす次第である。ちなみにこの「ごまかす」とは「ごまかし」の活用形で「ごまかし」とは「胡麻菓子」と書く。これは昔あった「胡麻胴乱(ごまどうらん)」という菓子の俗称で、この菓子が中空構造で「見掛け倒し≒ごまかし」であったことに由来しているが、ここでそんなことはどうでもいいことである。
SANYOのDSC-SX150というデジカメが手元にある。このデジカメは固定焦点150万画素ということで、今となってはカタログスペック的に見るところのない製品なのだが、その洗練された操作スタイル、レスポンス、画質には光るものがあった。私もしばらく愛用していたのだが、ひとつだけの欠点がバッテリーの持ちが悪いことである。このデジカメ、バッテリー室は単三型x2で、メタハイの使用が推奨されているが、イザとなったらアルカリも使用できるという、非常に私好みのスタイルなのである。しかしながら、それにつけても電池が持たな過ぎるのであった。
末期には電池を入れて数十秒でバッテリー警告等が点くようになったばかりか、電池室のフタが欠けてしまい、使い物にならなくなってしまった。前者の問題に関してはどうやら電池室の接点を掃除することで解決するらしいことを最近になって知ったのだが、既にリコーのCaplioG4wideに取って代わられてしまっているので、今となってはどうしようもないのである。
まず、このデジカメを車のアクセサリー電源に直結できるように改造してしまう(当然、3.3Vへの降圧はする、三端子レギュレータで一発である)。このデジカメ、メカニカルスイッチにより電源が入るのでON位置に固定しておけば、それだけで車の走行中、常にデジカメを起動しておくことが可能になるのである。さらにレリーズボタンから線を引き出し、PICマイコンから撮影を制御できるようにし、PICマイコンから1分間隔程度のインターバル制御でシャッターを切るわけである。
2005-06-08(Wed) 再び飲酒グワッシャ!!
昨日、オイラがゼビウスでシラフで進むことのできるエリアを再確認してみると書いたが、早速やってみた。サクサクとエリアをクリア、残機を1機を残した状態でエリア13まで進み、バックゾシーを越えるか越えないかあたりで撃墜された。今日こそ越えたと思ったんだがなぁ……後ろから飛来したゾシーを左に大きく回りこんだ先に、港の上のログラムから放たれた一発のスパリオが待ち受けていた。つーか、そこで弾を撃つか? もう20年以上の付き合いになるが、オマエさんソコまで性格ワルかったっけ?
ラスト1機は出撃直後に出現したブラグザカート群にあえなく撃墜。ちゅーか、キツすぎだぞブラグザカート。そんな近くで破裂されたら、絶対に避けれないっての。結局、オイラにとってはエリア13が鉄のカーテンであるコトを再確認させられた。ぐぅ。
さて、ゼビウスは置いておいて、工作しなきゃイカんモノはあるのだが、なんとなくいまひとつノリが悪い。そんなノリの悪い時、ノリを良くする薬効を持つのがビールである。ただし、薬というモノには副作用もあるわけで……早い話、ノリが良くなったせいでウイスキーのダブルを追加インストールしてしまい、今日もオーバラン、別の意味でガストノッチな気分になってしまったのであった。えーぃ、再グワッシャじゃッ!!
今日の酒量は昨日より控えめとはいえ、やはりアルコールはソルバルウの操縦に意外な影響を及ぼすようである。運もあるとは思うが、シラフならさすがにバキュラに激突死したりはしないと思うのだよな。また、酒を呑むと後半の攻撃に弱くなるようで、70%を越えているために次のエリアに進むとはいえ、そこで残機をすり減らしてしまう傾向があることがわかった。
2007-06-08(Fri) tDiary用「鉄塔認証」プラグイン完成
ちゅーわけで、tDiary用の「ゲイツ認証」プラグインが完成した。つーか、実は一昨日に記事を書いた時点でかなりの状態までできていたのだが。
で、一昨日の時点では「SVX認証」などという名称の予定であったが、この名前はヤメた。というのも、肝心の多数のSVXのイメージを十分な品質で揃えられなかったからである。オレ著作権で大量の同テーマの写真というと……実は昔こういうサイトを作っていたもんで……あるんですな、大量の「送電鉄塔」の写真が。というワケで「鉄塔認証」という名称にした。英語名「PylonAuth」。中国名「白竜逢瀬」(←ウソ)。
別にこのサイトに認証を適応するつもりはないが、ココで動作を試すことはできる。主に、検索エンジンやウェブアーカイバを排除するために作った認証方法である。
なお、CAPTCHAイメージはImageMagickのconvertコマンドを使って合成しているので、ちゃんと1枚のイメージになっており、こういうマヌケなコトにはなっていない。また、サーバで正解を保持するのはやっかいなので、認証情報はクライアントから送り返すようになっているが、正しくMD5を使っているので、理論的に破ることは十分に困難であると思われる。
認証に使うイメージの枚数は可変なので、それを8枚くらいにして、真にイメージの法則を知っている人間しか正しい選択ができないようにすれば、実用的な認証にもギリギリ利用できるかもしれない。もし、何らかの方法で1枚のイメージに2個のチェックを付けられるように工夫すれば、5枚で10ビットとなり1024通りだ。こうなれば数字3桁のCAPTCHAと同程度の防御率となる。
また、CAPTCHAイメージを毎回生成するとサーバの負荷がバカにならないので、頻度を下げ、過去のイメージを使いまわすことができるようにも作ってある。デフォルトでは新規生成は10回に1回、100個のイメージを保持し、使いまわすようになっている。
プラグインはGPLで公開する。プラグイン本体とサンプルの鉄塔認証データ。インストールの方法はmisc/plugin/pylonauth_plugin.rbにコメントとして書いてある。
2008-06-08(Sun) USBメモリを素因数分解する
オイラは以前にSIRENというメーカのUM-100-512SというUSBメモリを名指しで購入したのだが、最近になってそのチップがSLC構造だと知った。かなりの時を経てのイキナリのポイントアップだ。
オイラは過去に、特に下調べせずに買ったCD-RドライブであるCD-R56S-600、主力機が死んで慌てて買ったマザーボードであるCUB-Xと、かなり使い込んだ後で、それが名機であったことに気づかされることが度々あるが、それを想起させる。
で、改めてそれをモバイルCVSレポジトリにしようと思い、ゴチャゴチャとした中身を吸い出して、フォーマットしようとしたのだが、悩んだのがvfat領域をどうするかということ。やはり、ちょっと使いたい時のためにWindowsからも使える領域があった方がいい。
Disk /dev/sdc: 523 MB, 523632640 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 63 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes# time dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
dd: writing to `/dev/sdb': デバイスに空き領域がありません
1022721+0 records in
1022720+0 records out
523632640 bytes (524 MB) copied, 248.831 seconds, 2.1 MB/s
real 4m8.864s
user 0m0.742s
sys 0m3.612sDisk /dev/sdb: 523 MB, 523632640 bytes
17 heads, 59 sectors/track, 1019 cylinders
Units = cylinders of 1003 * 512 = 513536 bytes17 x 59 x 1019 x 512 = 523,293,184
523,632,640 - 523,293,184 = 339,456# man fdisk
-H heads
Specify the number of heads of the disk. (Not the physical
number, of course, but the number used for partition tables.)
Reasonable values are 255 and 16.
-S sects
Specify the number of sectors per track of the disk. (Not the
physical number, of course, but the number used for partition
tables.) A reasonable value is 63.799って素数っぽいけど、素数だっけ? 確かめるために「素数」でググる……わ。素数じゃないっぽいぞ。確か、デカい数値の素因数分解って、RSA暗号の基礎理論であり困難だと聞くが(ケタが違うって)……できるかいな。3で割って、7で割って……ダメだ。ヤケクソで17で割って……
# fdisk -H 47 -S 17 /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 523 MB, 523632640 bytes
47 heads, 17 sectors/track, 1280 cylinders
Units = cylinders of 799 * 512 = 409088 bytes
Disk /dev/sdb: 523 MB, 523632640 bytes
47 heads, 17 sectors/track, 1280 cylinders
Units = cylinders of 799 * 512 = 409088 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 3 1024 408289 83 Linux
/dev/sdb2 1025 1280 102272 6 FAT161シリンダのサイズが400KB程度と小さいから、先頭に空けておく領域も1MB以下で済んでいる。なんだよー、こんなことなら、プライマリドライブとして使っているコンパクトフラッシュも工夫すればよかったよ。
一方で、セカンダリドライブである16GBのSDカードは、16,071,000,064バイトだから……2^19×7×29×151……少し微妙だが、7と29を使えば、こっちもキッカリと使い切ることができる。うわぁ、フォーマットをやり直してぇ!!
922 get_kernel_geometry(fd);
923 get_partition_table_geometry();
924
925 heads = user_heads ? user_heads :
926 pt_heads ? pt_heads :
927 kern_heads ? kern_heads : 255;
928 sectors = user_sectors ? user_sectors :
929 pt_sectors ? pt_sectors :
930 kern_sectors ? kern_sectors : 63;